陣痛促進剤が保険適用になる場合とは?誘発分娩の出産費用を徹底解説

妊娠前、妊娠中の時、陣痛促進剤の使用が民間保険や健康保険の適用になるか気になりますよね。
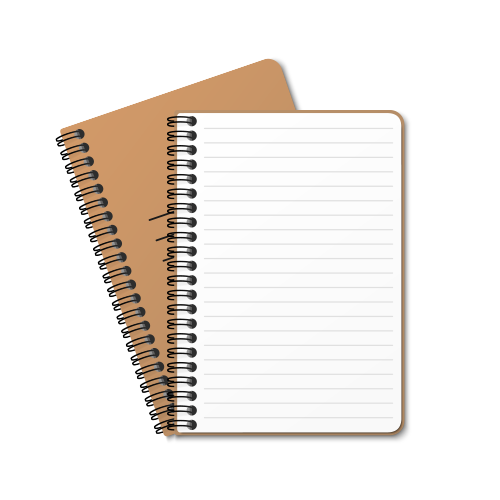
この記事の内容をまとめると
- 陣痛促進剤の費用は保険適用外の場合で1回あたり1~3万円ほどかかる
- 前期破水、長時間の微弱陣痛、母体の疾病などを理由に陣痛促進剤を使用した場合は保険適用となる
- 陣痛促進剤の使用が健康保険適用になれば高額療養費制度が利用できる可能性がある
この記事を見ることで陣痛促進剤を使用しても保険適用される可能性があることがわかり、不安を払拭した状態で出産に臨めるでしょう。
妊娠中の方、これから出産をお考えのあなたにおすすめ!
妊娠中でも入れる医療保険について詳しく見る
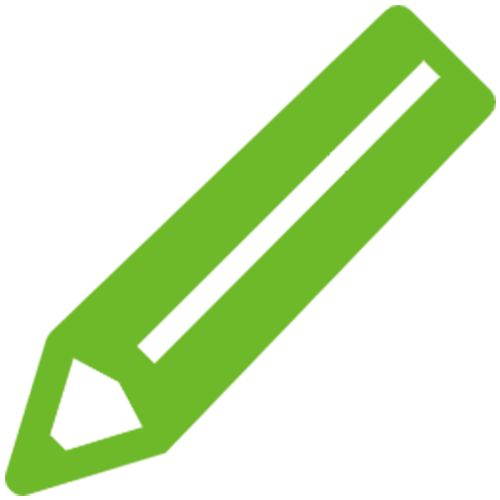 この記事の執筆者
この記事の執筆者

執筆者関野みき
SEOを意識した健康・美容・フィットネス・エンタメ・スポーツなどの記事を数多く執筆した経験あり。保険会社の帳票作成システムの開発経験があり、出産経験があり現在も育児中。
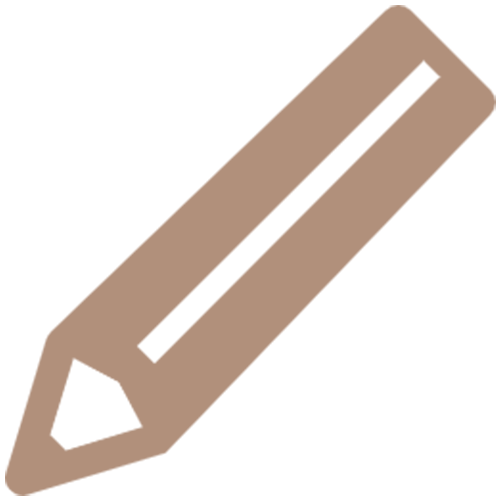 この記事の監修者
この記事の監修者

監修者ファイナンシャルプランナー 三浦希枝
FP3級を保持。保険会社に勤めていた経験を持ち、現在は、フリーライターとして独立起業し、3人の子供を育児中。大手メディアでの執筆経験やセミナー開催で講師の実績もあり。
陣痛促進剤を使った出産費用が保険適用になる場合とは
陣痛が弱くお産が進まないときや、予定したタイミングで分娩をおこないたいときなどに、子宮を収縮させて陣痛を起こす薬剤(陣痛促進剤・陣痛誘発剤)を使用することがあります。
陣痛促進剤(陣痛誘発剤)を使用した出産は、健康保険適用になる場合とならない場合があります。

陣痛促進剤を使うのはどんなとき?
陣痛促進剤(陣痛誘発剤)は、医学的には「子宮収縮剤」といいます。
既に始まっている陣痛を強めることを「陣痛促進」、まだ陣痛が始まっていない状態から陣痛を起こすことを「陣痛誘発」と言います。どのタイミングに使用するかにより陣痛促進剤、陣痛誘発剤と呼び方が変わりますが、薬剤自体は同じものです。
陣痛促進剤(陣痛誘発剤)は、次のようなときに使用されることがあります。
- 予定日超過
- 前期破水
- 長時間の微弱陣痛
- 母体の疾病
- 赤ちゃんの子宮内感染
- 計画分娩
計画分娩は、「夫の休みに合わせて出産したい」「自宅から病院までが遠く病院に着く前に生まれてしまうのではと不安」などの理由により、あらかじめ日にちを決めて誘発分娩をおこなうことです。
また、医療機関によっては無痛分娩を希望した場合に、計画分娩になることがあります。これは、すべての医療機関が24時間いつでも無痛分娩に対応できるわけではないためです。
陣痛促進剤が保険適用になる場合とは
健康保険が適用されるのは、既に起こっている異常に対し医療行為をおこなった場合です。
そのため、なんらかの異常(前期破水・長時間の微弱陣痛・妊娠高血圧症候群など)を理由に、早く出産を終えなければならないという医学的判断で陣痛促進(陣痛誘発)がおこなわれた場合は、健康保険が適用されます。
一方で、異常がおこる前の段階で、異常の予防を目的としておこなわれた陣痛促進(陣痛誘発)は健康保険適用外です。

予定日超過で陣痛誘発剤を使用しても、そのあと異常なく出産を終えたのであれば健康保険は適用されません。
【実例紹介】陣痛促進剤を使った誘発分娩、いくらかかった?
陣痛促進剤(陣痛誘発剤)を使用した場合、健康保険適用外の価格は医療機関により異なりますが1回1~3万円ほどが相場です。
陣痛促進剤を使った誘発分娩の実例
健康保険適用の場合は促進分娩(誘発分娩)にともなう入院費、検査費なども3割負担になります。費用例は以下の通りです。
| 内容 | 金額(3割負担) |
|---|---|
| 入院費(2日間) | 1万1,430円 |
| 点滴(陣痛促進剤) | 2,040円 |
| 検査 | 3,500円 |
| 食事(1食460円) | 2,760円 |
| 合計 | 1万9,730円 |
陣痛促進剤を使った誘発分娩、いくらかかる?
陣痛促進剤の費用はそこまで高額にはなりませんが、前処置の有無や経口薬の使用など内容により金額は変わります。また、有効陣痛がなかなかつかず入院が長引けば、それだけ入院費や食事代がかかるため費用が高額になる可能性もあります。
なお、陣痛促進剤が健康保険適用になった場合でも、分娩介助料や赤ちゃんにかかる費用はすべて自費となります。
他にも分娩後の入院費(5~7日間程度)、産科医療補償制度の掛け金、食事代、差額ベッド代など、合計で40~60万円ほどかかります。自費の部分は地域や医療機関により金額の差が大きく、特に個室の設備やサービスが充実している個人病院ではもっと高額になることもあるでしょう。

ほとんどの医療機関では出産育児一時金の直接支払制度に対応しているため、実際の窓口負担は出産育児一時金を差し引いた金額になります。
誘発分娩の手順|陣痛促進剤以外にかかる費用とは?
誘発分娩・促進分娩の方法は、子宮収縮剤の投与だけではありません。子宮頸管の拡張や人工破膜(人工的に破水させること)がおこなわれることもあります。
ここでは、どのようなときにどのような処置をおこなうのか、誘発分娩・促進分娩の詳しい内容と手順をご紹介します。
誘発分娩の手順【1】子宮頸管を拡張する
まず内診して、子宮頸管が熟化しているか(子宮口が柔らかく開きやすい状態になっているか)調べます。もし熟化が不十分であれば、子宮頸管拡張器を使って子宮頸管を拡張します。
主に使用される器具は、12時間ほどかけて水分を吸収して膨らむ「ラミナリア桿(かん)」、ゴムの風船に水を入れて膨らませる「メトロイリンテル」の2種類です。メトロイリンテルはその形状から「バルーン」と呼ばれることもあります。
子宮頸管拡張の処置は「子宮頸管拡張及び分娩誘発法」といい、金額は以下の通りです。
| 拡張器の種類 | 診療報酬点数※ | 金額(3割負担) |
|---|---|---|
| ラミナリア | 120点 | 360円 |
| メトロイリンテル | 340点 | 1,020円 |
※1点=10円
※2022年現在の点数
誘発分娩の手順【2】子宮収縮剤を使用する
子宮収縮剤はプロスタグランジン系(経口薬または点滴)とオキシトシン系(点滴のみ)があり、どちらも分娩時に分泌されるホルモンと同様の成分です。
様子を見ながら徐々に量を増やしていくため、子宮収縮剤を使用した途端に急激な陣痛が起こってすぐお産が進むというわけではありません。
もちろん中には一気にお産が進む人もいますが、朝から陣痛誘発を開始し夕方になっても分娩が進行しないことも珍しくありません。その場合は一度中止して翌朝再開することになります。状態によっては、一旦退院となることもあります。
誘発分娩の手順【3】人工破膜をおこなう
子宮頸管の拡張や子宮収縮剤でも陣痛が弱い場合には、人工破膜をおこなうこともあります。
人工破膜は人工的に卵膜を破って破水を起こす処置で、子宮内容量が減ることで刺激になりお産が進みます。

人工破膜は、基本的に子宮口が開き赤ちゃんが下がってきているのに陣痛が弱くお産が進まないときに、最後の一押しとしておこなわれる処置です。
陣痛促進剤を使った出産費用は高額医療費支給制度の対象?
陣痛促進剤・陣痛誘発剤を使用した出産費用のうち、健康保険適用となった部分については高額療養費制度(高額医療費支給制度)の対象になります。
ここからは、より詳しく陣痛促進剤の使用と高額医療費支給制度の関連性について紹介していきます。
同一の健康保険に加入する家族(70歳未満)が複数の医療機関に受診した例
| 夫 | A病院 | 4月1日 | 外来・医科 | 1万円 | 合計2万3,000円(合算) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 院外処方 | 3,000円 | |||
| 4月8日 | 外来・医科 | 1万円 | |||
| B病院 | 4月5日 | 外来・医科 | 2万5,000円 | 2万5,000円(合算) | |
| 4月10日 | 外来・歯科 | 1万円 | 1万円(合算不可) | ||
| 妻 | A病院 | 4月3日 | 入院・医科 | 5万円 | 5万円(合算) |
| 4月25日 | 外来・医科 | 2万円 | 2万円(合算不可) |
上記の場合、自己負担額の世帯合計は2万3,000円+2万5,000円+5万円=9万8,000円なので、自己負担限度額が8万円であれば1万8,000円の還付を受けられます。
高額療養費制度とは
高額療養費制度は1ヶ月(1日~末日まで)の医療費が自己負担限度額を超えた場合に、その超過分の払い戻しを受けられる制度です。自己負担限度額は所得により異なりますが、一般的な所得の人であれば約8万円、高所得者は20万円以上になることもあります。
誘発分娩(促進分娩)だけで自己負担限度額を超えることはまれですが、同一の健康保険に加入する被保険者・被扶養者の自己負担額は合算できるため、家族の医療費もあわせて確認してみると良いでしょう。

自己負担額は受診者ごと、医療機関ごとに算出し、同じ医療機関であっても入院・外来・医科・歯科は分けて計算します。なお、院外処方の薬剤費等は、処方箋を発行した医療機関の自己負担額と合算します。
まとめ:陣痛促進剤を使った出産費用は保険適用の可能性あり
前期破水、長時間の微弱陣痛、妊娠高血圧症候群などにより陣痛促進剤を使用した場合は健康保険が適用されます。
健康保険が適用されれば陣痛促進剤の費用はそこまで高額にはなりませんが、なかなか陣痛が起きずに入院が長引けば結果的に費用が高額になることもあります。民間保険の給付金がおりれば金銭的なゆとりが得られますので、安心して出産に臨みたい方は加入を検討してみましょう。
出産はイレギュラーな出費が発生しやすいライフイベントです。どのように備えるか、パートナーとしっかり話し合っておきましょう。

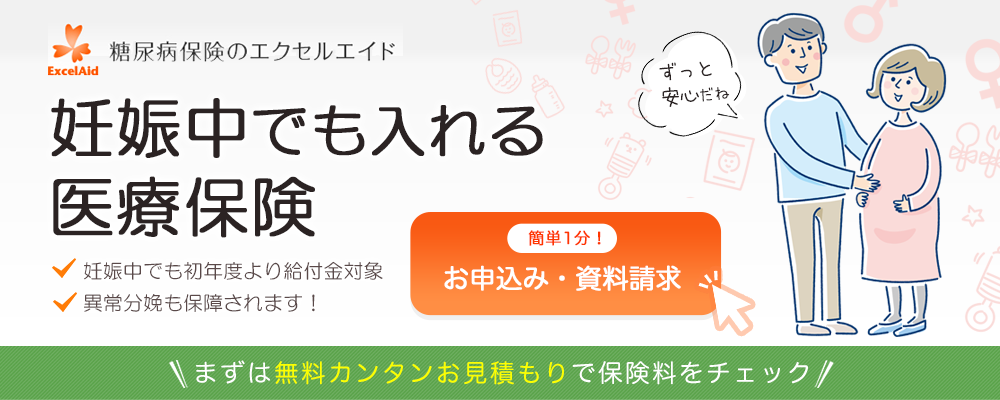
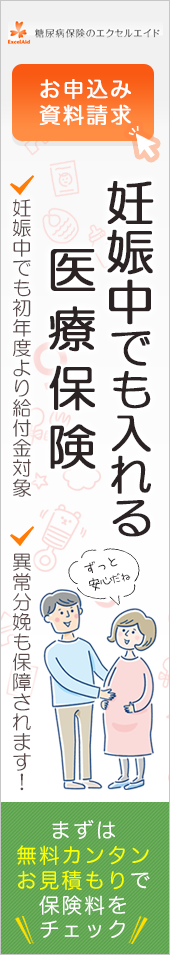
健康保険が適用されるケースでは、民間の医療保険から給付金がおりる可能性があります。保険商品により保障範囲が異なるため、健康保険適用になった場合は保険会社に問い合わせてみると良いでしょう。