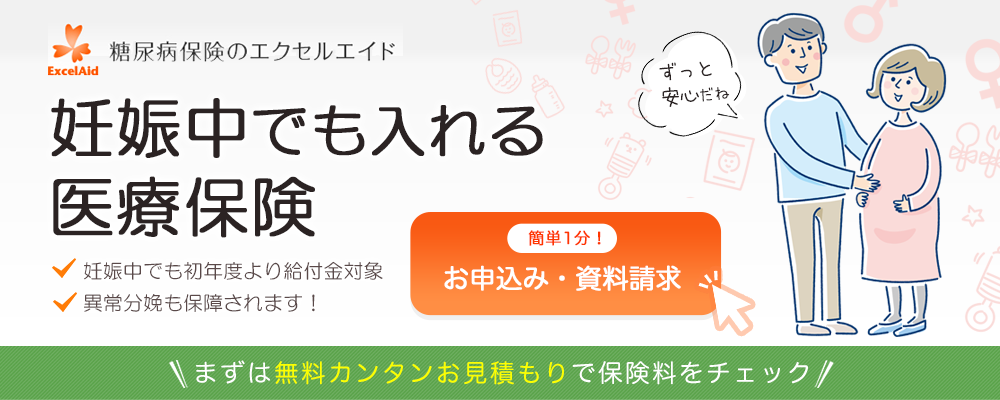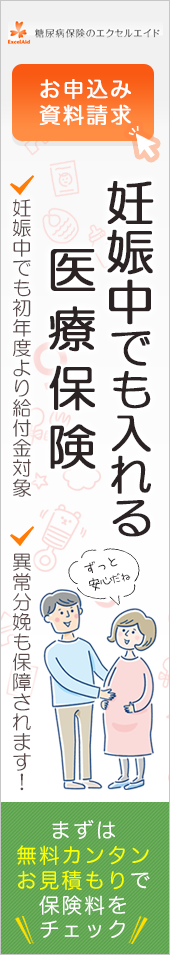

妊娠後いつまで仕事ができる?仕事を続けるための注意点と役立つ制度を紹介
妊娠をした際に、いつまで仕事を続けられるのか気にされる方も多いのではないでしょうか。
産休の取得期間から仕事を続けるうえでの注意点、妊婦に役立つ便利な制度まで詳しく紹介するので、ぜひ参考にしてください。
産休が取得できる時期
働く女性のために、妊娠・出産に伴う休暇制度として産休制度が用意されています。
産休は産前に42日間、産後に56日間取得可能で、双子以上の多胎の場合は産前に98日間の休暇取得が可能です。
産後休暇の取得は必須となっていますが、産前休暇は任意で取得となっています。
つまり、産前の休暇は自分の好きなタイミングで取得可能で、体調と相談しながら休暇に入る時期を決められます。
仕事を続ける期間は体調に合わせて決める
産前の休暇は取得期間が決められているわけではないので、働こうと思えば出産直前まで働くことも可能です。
ただし、妊娠をすると体調に不調をきたすことも多いので、無理はしすぎないようにしましょう。
妊娠初期はつわりの症状により吐き気や息切れを起こしやすく、妊娠中期に入ると少しずつお腹が出てきて立っているのも辛いことがあります。
妊娠後期になると、さらにお腹が大きくなりお腹が張りやすくなってきます。
体調が優れない時は無理せず、身体を休めるようにしましょう。
職場には余裕を持って妊娠の報告を行おう
妊娠後も仕事を続けていくためには、周囲のサポートも欠かせません。
事前に妊娠の報告をしておくことで、妊婦でも働きやすいよう仕事時間や仕事内容を調整してくれるケースもあります。
また、妊娠していることを伝えておけば、急な体調変化が起こっても気兼ねなく休みを取得しやすくなります。
産休を取得するとなると長期間仕事から離れることになり引き継ぎも必要になるため、職場に迷惑をかけないためにも妊娠の報告は余裕を持って行うのがベストです。
母性健康管理指導事項連絡カードを活用する
妊娠中も仕事を続けていくのであれば、母性健康管理指導事項連絡カードを活用すると良いでしょう。
母性健康管理指導事項連絡カードとは、医師の指導内容を適切に事業主に伝えるためのツールです。
医師が妊婦の体調を診て仕事の緩和や休息などが必要な場合は、その旨を医師が母性健康管理指導事項連絡カードに書いてくれます。
母性健康管理指導事項連絡カードを受け取った事業主は記載内容に合わせた措置を行う必要があり、医師の指導に基づいた適切な労働環境で仕事を続けることができます。
まとめ
妊娠後も仕事を続ける場合は、無理をしないことが何より大切です。
妊娠中は体調の変化も起こりやすくなっているので、しんどいときは遠慮せず周囲に助けを求めましょう。
母子の健康を第一に考え、無理をしないことを心がけましょう。
こちらの記事もおすすめです
当サイトでは、弊社が取扱う損害保険会社および生命保険会社の各種商品の概要について解説し、ご紹介しております。
この保険商品一覧に記載されている内容は、条件等により適用されない場合があります。
保障内容・保険料等の保険商品の詳細につきましては、必ず各保険会社が提供する契約概要やパンフレット等、をお取り寄せいただき、「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」等、または保険会社のWEBサイトをインターネットで必ずご確認ください。
- 取扱・募集代理店 株式会社エレメント
- 〒212-0052 神奈川県川崎市幸区古市場1-15
- 電話番号 044-522-5586