帝王切開にはいくらかかるの?給付金は?医療保険がおすすめの理由

これから出産を控え、帝王切開の手術も想定して取り組んでみようと考えているタイミングで、帝王切開による手術で国や民間保険会社からいくらもらえるのか気になると思います。
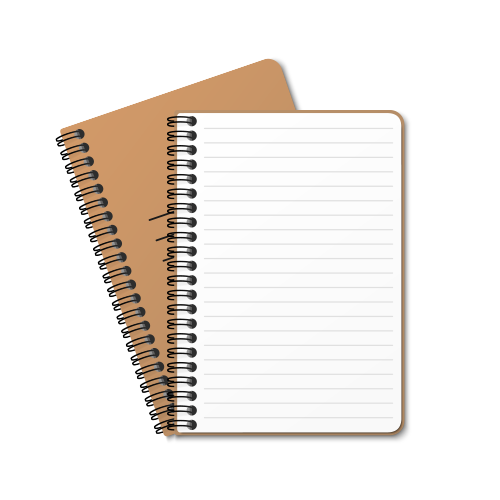
この記事の内容をまとめると
- 帝王切開は意外に金銭負担が大きい
- 国からもらえる公的医療保険だけでなく、民間医療保険の加入が望ましい
- 民間医療保険には安くてしっかり保障されるものもたくさんある
この記事を見る事で帝王切開にかかる費用はいくらか、またどのようにすればリスクを抑えられるか理解し安心して出産に臨めるでしょう。
妊娠中の方、これから出産をお考えのあなたにおすすめ!
妊娠中でも入れる医療保険について詳しく見る
帝王切開で医療保険に入ってないといくらかかる?
まず前提として、自然分娩の場合についてです。自然分娩とは医療介入をせず、自然の流れに沿った出産のことをいいます。一般的に自然分娩の費用は40~80万円程度とされており、原則として健康保険は適用されません。そのため入院費なども全て自費となります。
ここでは自然分娩ではなく帝王切開の際に一般的にかかる費用がどのくらいなのか、選択(予定)帝王切開の場合と緊急帝王切開の場合に分けてご説明します。
選択(予定)帝王切開
選択(予定)帝王切開は、妊婦のお腹をメスで切り、膣を経由せずに赤ちゃんを取り出す出産のことを帝王切開分娩といいます。帝王切開分娩は健康保険が適用される医療行為です。
平成28年の診療報酬点数表によると、地域や医療機関の違いに関係なく、あらかじめ予定して行われる選択帝王切開の費用は20万1,400円となっています。そこから健康保険の適用により、自己負担は3割となります。

緊急帝王切開
平成28年の診療報酬点数表によると、緊急帝王切開の費用は選択帝王切開の場合とは異なり、22万2,000円となります。
帝王切開での出産?医療保険をおすすめする理由
前述の通り、帝王切開には医療保険が適用されます。そのため入院費など帝王切開にかかる費用を抑えるには、医療保険に入っているかどうかがポイントとなります。ここでは医療保険の種類と、民間医療保険に加入するメリットについて解説します。
医療保険の種類
医療保険には公的医療保険と、民間の医療保険の2種類があります。公的医療保険とは、国民健康保険などの健康保険のことです。
日本には国民皆保険の制度がありますよね。国民一人ひとりが加入している保険の運営主体は市町村・会社・組合など様々です。しかし原則として全ての国民が所得に応じた保険料を支払い、何らかの公的医療保険に加入しています。
一方、民間の医療保険は任意加入です。保険の運営主体は民間の保険会社で、必要に応じて加入することができます。ただし健康状態および年齢等によっては加入できないこともあります。

民間の医療保険の保障内容は保険会社や保険商品によって様々です。保険料は健康状態・年齢・性別・支払い方法などによって異なります。
民間医療保険のメリット
民間の医療保険に加入していて、入院したり手術を受けたりした場合、給付請求の手続き後に所定の給付金が現金で給付されることになります。給付事由は所定の制限がありますが、給付金の使途について制限されることはありません。
そのため民間医療保険の給付金によって、公的医療保険の自己負担分や、その他の治療に付随してかかる費用をカバーすることも可能です。医療における備えはまず公的医療保険をベースとし、それだけではカバーできない部分を民間の医療保険で補完できると考えると分かりやすいでしょう。
また現代の医療技術は日進月歩で進歩しており、民間の医療保険もそれに合わせて改定あるいは新商品の発売が繰り返されています。以前に加入した民間の医療保険では給付対象となっていなかった手術でも、新しい商品では給付対象となっているというケースも少なくありません。

民間の医療保険を毎年のように頻繁に見直す必要はありませんが、ライフスタイルの変化が生じた時などは、その時の医療保険のトレンドを確認して必要に応じて見直すことも検討しておきましょう。
帝王切開で給付金はいくらもらえる?民間医療保険「エクセルエイド」を紹介
実際に民間の医療保険に加入している場合、帝王切開の際にどれくらいの給付金がもらえるのでしょうか?ここでは民間の医療保険の中でも特におすすめなエクセルエイドの保険で、どれくらいの給付金が受け取れるのかご紹介します。
エクセルエイドの保険
エクセルエイドの普通保険では、現在妊娠中の方も週数に関わらず加入することが可能です。また妊娠中の方でも初年度より給付金の支払い対象となっています。もちろん帝王切開等の異常分娩も保障の対象となっており、妊娠中の方から大きな好評を得ています。
エイクセルエイドの普通保険の保障内容は入院給付金が5,000円×入院日数。また入院中の手術の場合は50,000円の手術給付金が受け取れます。
帝王切開による出産一時金(出産育児一時金)と高額医療費(高額療養費)「申請書はどこでもらえる?」
出産時に利用できる公的補助制度は様々なものがあります。ここではその中から出産育児一時金と高額療養費制度について、受け取り方法など詳しくお伝えします。
出産一時金(出産育児一時金)
医療保険の被保険者およびその被扶養者が出産した場合、子ども1人につき42万円の出産育児一時金が支給されます。ちなみに出産一時金と勘違いしている方も少なくないのですが、出産育児一時金が正式な名称です。
出産育児一時金の適用には、妊娠4ヶ月(85日)以降での出産が条件となっています。自身あるいは配偶者が加入している健康保険組合・共済組合に申請を行います。
高額医療費(高額療養費)
高額療養費制度とは1ヶ月間にかかった医療費の自己負担額が高額となった際に、年齢や所得などから設定される自己負担限度額を超えた金額が払い戻される制度です。ちなみにこちらも高額医療費と勘違いされてる方が多いのですが、高額療養費というのが正式な名称となっています。
高額療養費制度は自然分娩の場合は利用できません。しかし帝王切開分娩や切迫早産などの医療行為を受けた際には利用することが可能です。こちらは診療報酬明細書の審査後、健康保険より支払われます。
まとめ:帝王切開での出産?医療保険をおすすめする理由
この記事では帝王切開でかかる費用についてや、なぜ医療保険の加入が望ましいのか。またおすすめの民間医療保険についてもご紹介しました。
最後までこの記事を読むことで帝王切開の金銭負担が思った以上に大きいことや、民間医療保険にも安くてしっかり保障されるものがあることを理解していただけたかと思います。
もし民間の医療保険に加入していなければ、帝王切開の際も公的医療保険による保障しか受けることができません。出産の際には万が一に備えて、金銭的にも万全の準備をしておきましょう。

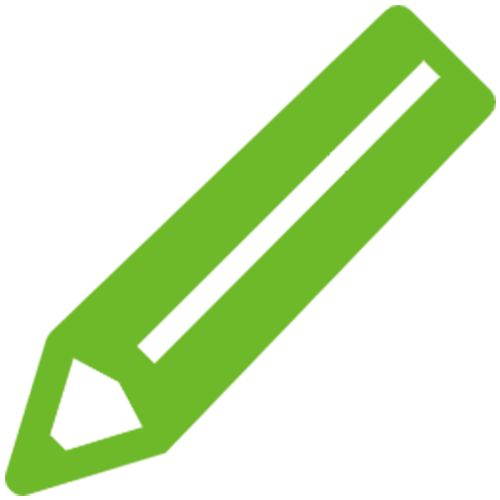 この記事の執筆者
この記事の執筆者
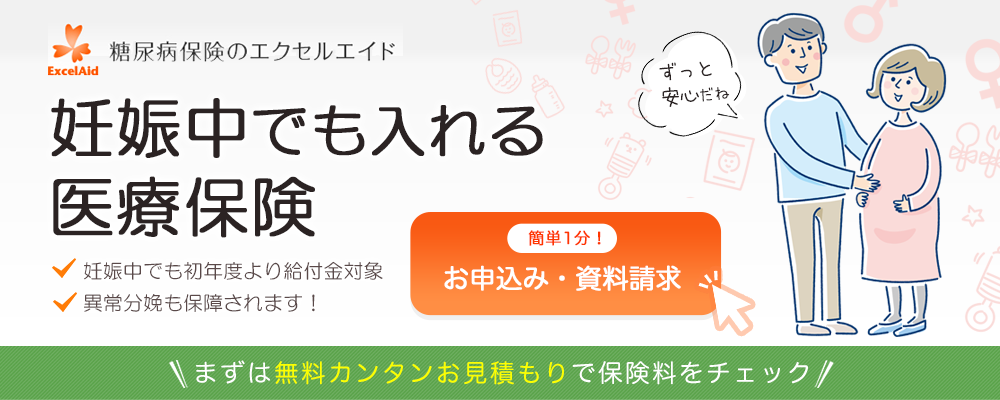
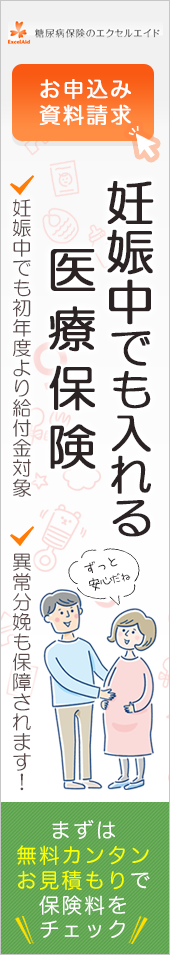
帝王切開分娩は自然分娩より入院期間が長くなる傾向があるため、自己負担の総額はおよそ40~100万円程度となるでしょう。