出産前後の社会保険手続き一覧|出産手当金、扶養追加など詳しく解説

この記事を見ているあなたは「出産に際して必要な社会保険手続き」や「社会保険手続きによりもらえるお金」について知りたいとお考えではありませんか。
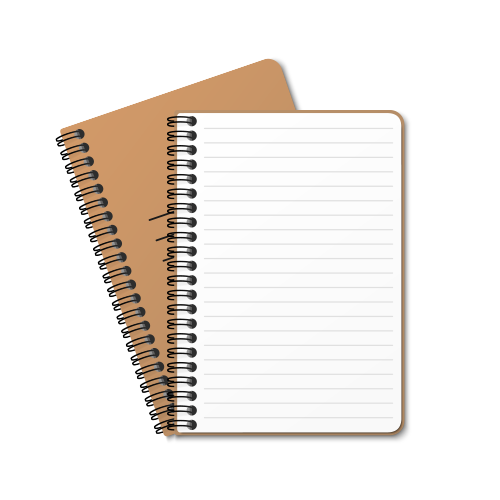
この記事の内容をまとめると
- 出産前後には出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金、社会保険料免除、子どもの健康保険加入(扶養追加)などの社会保険手続きが必要
- 自治体、共済組合、健康保険組合から出産祝い金を貰えることがある
この記事を読むことで、出産前後にもらえるお金や必要な社会保険手続きがわかり、「もらえるはずのお金をもらえなかった」という事態を防ぐことができるでしょう。
妊娠中の方、これから出産をお考えのあなたにおすすめ!
妊娠中でも入れる医療保険について詳しく見る
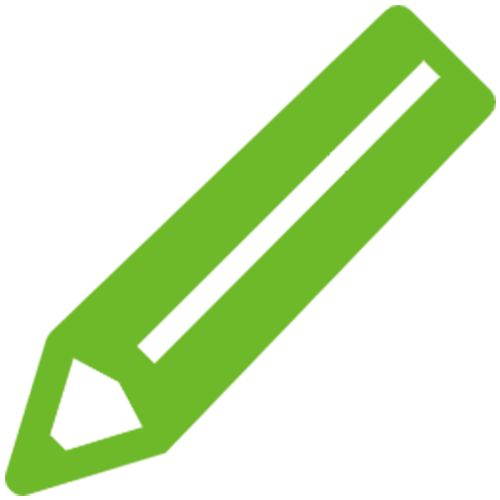 この記事の執筆者
この記事の執筆者

執筆者関野みき
SEOを意識した健康・美容・フィットネス・エンタメ・スポーツなどの記事を数多く執筆した経験あり。保険会社の帳票作成システムの開発経験があり、出産経験があり現在も育児中。
出産でもらえるお金と社会保険手続き一覧|出産育児一時金、出産手当金等
子どもができると、多くの社会保険手続きが必要になります。しかし、いつどのような手続きをすれば良いのか、手続きに際してどのような書類が必要なのかなど、わかりづらい部分も多いのではないでしょうか。
ここでは出産にともなう以下の社会保険手続きについて、詳しく解説します。すべてお金にかかわることなので、漏れのないようにしっかりチェックしてください。
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 育児休業給付金(育休手当)
- 社会保険料免除
出産育児一時金
出産育児一時金は、子どもが生まれたときに健康保険から42万円(令和4年8月現在の金額)が支給される制度です。子ども1人につきの金額なので、双子は2倍、三つ子は3倍の金額を受け取れます。
最近では、出産する医療機関に出産育児一時金が直接支払われる「直接支払制度」に対応している医療機関がほとんどです。

| 給付金額 | 42万円(令和4年8月現在)※産科医療補償制度対象外の場合は40.8万円 |
|---|---|
| 給付条件 |
|
| 申請者 | 医療機関 |
| 本人の手続き時期 | 出産前 |
| 本人が用意する書類 | なし |
| 本人がやること | 直接支払制度に対応しているか医療機関に確認する |
まれに直接支払制度に対応していない小規模施設もありますが、その場合は「受取代理制度」を利用できることがあります。受取代理制度も、直接支払制度と同じく出産育児一時金が医療機関に直接支払われますが、請求手続きは本人がおこなわなければなりません。
受取代理制度を利用する場合
| 申請者 | 本人 |
|---|---|
| 本人の手続き時期 | 出産予定日の2ヶ月前以降 |
| 本人が用意する書類 | 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用) |
| 本人がやること |
|
なお、直接支払制度・受取代理制度のいずれかを利用し、出産費用が出産育児一時金を下回ったときは、差額を受け取ることができます。直接支払制度の場合は、健康保険組合等に申請が必要です。受取代理制度の場合は、特に手続きは必要ありません。

直接支払制度や受取代理制度を利用できない・しない場合は、出産費用を医療機関に全額支払ったうえで健康保険組合等に申請します。給付を受ける権利は出産日の翌日から2年を経過すると時効により消滅するため、早めに申請しましょう。
出産手当金
出産手当金は、産前産後休業を取得する被保険者が条件を満たすと受け取れる手当金です。
公務員は産前産後休業中であっても給与支払いがあるため、ここでは会社員を前提として解説します。
| 給付金額 | 1日あたり:賃金(日額)の2/3相当額(※1) |
|---|---|
| 支給期間 | 労働基準法第65条に定められる産前産後休業期間(※2)のうち、産前産後休業を取得し給与支払いがなかった、または少なかった期間 |
| 給付条件 |
|
| 申請者 | 会社 |
| 本人の手続き時期 | 産後休業終了後※産前分・産後分など複数回に分けて申請することも可能 |
| 本人が用意する書類 | なし |
| 本人がやること |
|
産前産後休業中に給与を受け取っている場合でも、出産手当金の金額より少なければ差額を受け取れます。また、産前産後休業中に会社を退職する場合でも、条件を満たせば出産手当金の給付を受けられます。詳細は、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。
※出産手当金の支給開始日以前12ヶ月間の各標準報酬月額の平均額÷30日×2/3(被保険者期間が12ヶ月に満たない場合の計算方法は協会けんぽ「出産手当金について」が参考になります)
※出産日(出産日が予定日以降の場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日の翌日以降56日まで
育児休業給付金(育休手当)
育児休業給付金(育休手当)は、育児休業を取得する被保険者が条件を満たすと受け取れる給付金です。
| 給付金額 | 1日あたり:賃金(日額)の2/3相当額(※1)※育児休業開始から6ヶ月が経過した後は1/2相当額※限度額あり(※2) |
|---|---|
| 支給期間 | 1歳に満たない子を養育する育児休業期間中で給与支払いがなかった、または少なかった期間※両親が育休を取得する場合、条件を満たせば1歳2ヶ月まで延長可(パパ・ママ育休プラス)※保育所に入所できないなどの場合は最長2歳まで延長可 |
| 給付条件 |
|
| 申請者 | 会社 |
| 本人の手続き時期 | 産前産後休業に入る前~育児休業中※初回以降、2ヶ月毎の申請(希望があれば1ヶ月毎) |
| 本人が用意する書類 |
|
| 本人がやること |
|
※1 育児休業開始前6ヶ月間の賃金総額を180で割った金額×支給日数×67%(育児休業開始から6ヶ月経過後は50%)
※26ヶ月まで30万5,319円、6ヶ月経過後22万7,850円(令和4年8月現在の金額、毎年8月1日に改定)
※3 育児休業開始日前日から1ヶ月ごとに区切った期間(4月15日~5月14日など)
※4 該当完全月が12ヶ月に満たない場合は、賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある完全月も含む
育児休業中に事業主から賃金が支払われる場合は、次のような扱いになります。
- 賃金が賃金月額の13%(6ヶ月以降は30%)以下→通常通り支給
- 賃金が1.を超えて80%未満→賃金月額の80%相当額と受け取る賃金の差額を支給
- 賃金が賃金月額の80%以上→支給されない
令和4年10月からは、産後パパ育休(出生時育児休業)制度が創設され、パパが子どもの出生後8週間以内に最長4週間(2回に分割可)の育児休業を取得できるようになります。産後パパ育休を取得した場合は、出生時育児休業給付金を受け取れます。
育児休業給付金については少し複雑なため、詳しくは下記URLをご確認ください。
社会保険料免除
産前産後休業中や育児休業中は、健康保険・厚生年金保険料の支払いが免除される制度があります。
産前産後休業中の社会保険料免除
| 申請者 | 会社 |
|---|---|
| 免除期間 | 産前産後休業開始月から終了前月まで(産後休業の終了日が月末日の場合のみ終了月まで) |
| 本人の手続き時期 | 産後休業中 |
| 本人が用意する書類 | なし |
| 本人がやること | ・出産前:出産予定日を勤務先に伝える・出産後:出産日と生まれた子供の名前を勤務先に伝える |
育児休業中の社会保険料免除
| 申請者 | 会社 |
|---|---|
| 免除期間 | 育児休業開始月から終了前月まで(育児休業の終了日が月末日の場合のみ終了月まで) |
| 本人の手続き時期 | 出産後 |
| 本人が用意する書類 | なし |
| 本人がやること | 出産日と生まれた子供の名前を勤務先に伝える |
産前産後休業期間中であれば有給・無給問わず社会保険料は免除になります。また、平成31年4月からは国民年金第1号被保険者が出産した場合に、国民年金保険料が免除されるようになりました。
国民年金第1号被保険者の国民年金保険料免除
| 申請者 | 本人 |
|---|---|
| 免除期間 | 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠は3ヶ月前から6ヶ月間) |
| 本人の手続き時期 | 出産予定日の6ヶ月前以降 |
| 本人が用意する書類 |
|
| 本人がやること | 市区町村の役所(国民年金の窓口)に国民年金被保険者関係届書(申出書)、年金手帳などの必要書類を提出 |
なお、将来の年金額を計算する際は、免除期間中も保険料を納めた期間として扱われます。
健康保険から出産祝い金がもらえることもある?協会けんぽは?
公務員が加入する共済組合では、組合員が出産したときに「出産費附加金」、被扶養者が出産したときに「家族出産費附加金」が支給されることがあります。附加金の有無や金額は共済組合により異なるため、詳細は加入している共済組合へご確認ください。
共済組合とは別に、互助会(互助組織)から出産祝い金が支給されることもあります。
健康保険組合については出産育児一時金の他に数万円の付加給付をもらえる場合もありますが、協会けんぽは残念ながら今のところ出産祝い金や付加給付などはありません。

ただし、健康保険組合や協会けんぽからの給付がなくても、お住まいの市区町村によっては自治体から出産祝い金や、商品券、おもちゃ、絵本などのプレゼントをもらえることがあります。
子どもが生まれたら必要な社会保険手続き|健康保険の加入(扶養追加)
赤ちゃんが生まれたら、速やかに健康保険の扶養追加手続きをおこなう必要があります。両親が共働きの場合は、収入が多い方の扶養に入れるのが原則です。会社の総務部などに申請して、赤ちゃん名義の保険証を作ってもらいましょう。
| 申請者 | 会社 |
|---|---|
| 本人の手続き時期 | 出産後すぐ |
| 本人が用意する書類 | 母子手帳や出生証明書の写し(会社により異なる) |
| 本人がやること | 生まれた子どもの名前を勤務先に伝える |
保険証の発行には大体1~2週間かかります。保険証を受け取ったら、お住まいの市区町村の役所で乳幼児医療助成の医療証交付申請も忘れずにおこなってください。
自営業など、両親が国民健康保険に加入している場合は、「扶養」の概念がないため赤ちゃんも被保険者として国民健康保険に加入します。扶養ではないため、赤ちゃんの保険料も支払う必要があることを覚えておきましょう。

国民健康保険の加入手続きは、住民票のある市区町村の役所でおこなってください。出生届や児童手当金の手続きとあわせて、出生後2週間以内におこなうのがおすすめです。
国民健康保険に加入する場合
| 申請者 | 本人(親) |
|---|---|
| 本人の手続き時期 | 出産後すぐ |
| 本人が用意する書類 | 母子手帳、申請者の身分証明書、印鑑(自治体による) |
| 本人がやること | 出生後2週間以内を目安に役所で手続きをする |
赤ちゃんの1ヶ月健診までには、保険証と医療証が手元に届くようにしておきましょう。1ヶ月健診は原則自費なので保険証や医療証がなくても問題ないと思われがちですが、なんらかの異常が見付かれば保険診療もあり得ます。
もし保険証がなくても後から返金はしてもらえますが、最初から保険証があった方がスムーズなので手続きは早めにおこなうと良いでしょう。
まとめ:出産前後の社会保険手続きを知ってお金のもらい損ねを防ごう
妊娠・出産に際して、たくさんの社会保険手続きが必要になります。ただし、産後直後のママは見た目ではわからなくても体の中はボロボロの状態です。パパができる手続きは、ぜひパパが率先しておこなうようにしてください。
産褥期(産後6~8週間)に安静にしていないと、子宮復古不全や産褥熱などの症状が出たり骨盤のゆがみが生じたりして、後々まで影響が残ることもあります。
妊娠・出産にともなう社会保険手続きはいずれもお金に関わるものなので、本記事を参考に手続きの時期や必要なものをしっかり把握して、漏れのないよう準備しておきましょう。

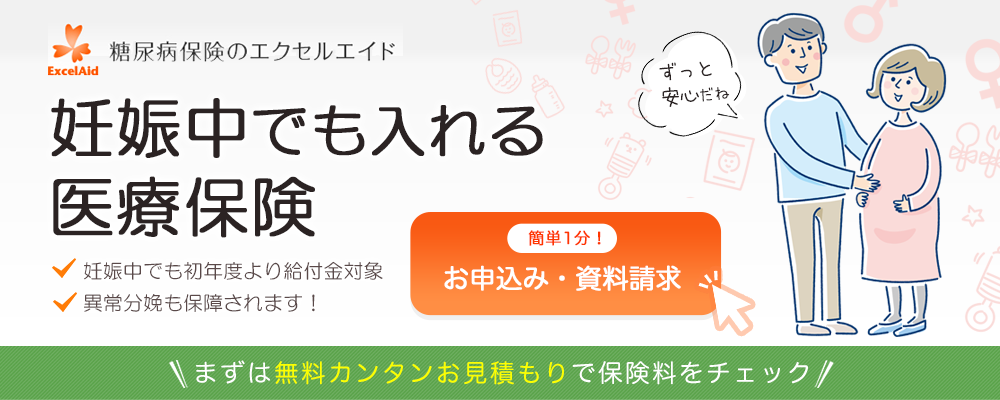
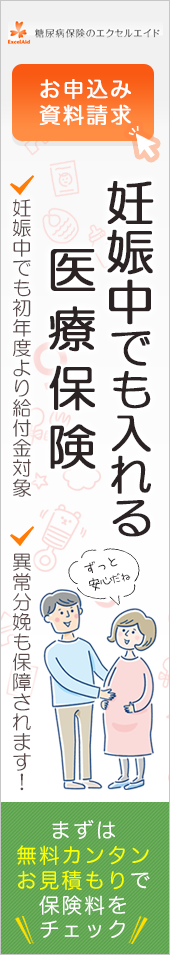
直接支払制度を利用する場合、本人がおこなう手続きは医療機関から渡される合意書の記入だけです。その後の請求手続きや受け取りは医療機関がおこなうため、本人は医療機関の会計窓口で出産費用から出産育児一時金を差し引いた金額を支払えば良く、まとまった額の現金を用意する必要がなくなります。