流産手術は保険適用?日帰り入院と外来で費用や給付金はいくら違う?

流産手術に民間保険や健康保険が適用されるか、また給付金がいくらおりるか気になりますよね。
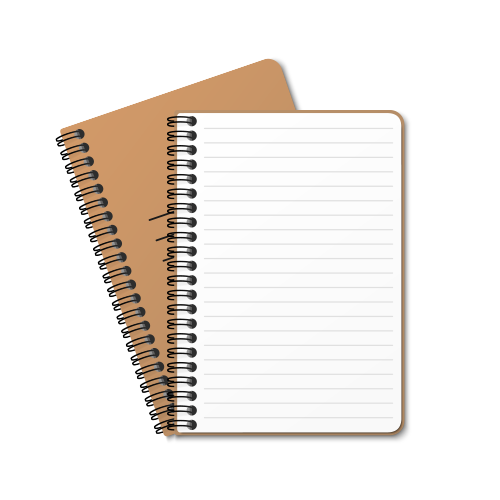
この記事の内容をまとめると
- 稽留流産、不全流産の手術費用は民間保険や健康保険が適用される
- 流産手術で民間保険からおりる可能性がある給付金は、入院給付金、手術給付金、女性疾病特約の給付金、通院給付金
- 流産手術の費用は早期流産なら1~5万円程度、後期流産は45万円+埋葬料2万円程度
- 後期流産は出産育児一時金、出産手当金の支給対象
この記事を見る事で万が一流産になっても保険適用されることがわかり、安心して妊娠生活をおくる事ができるでしょう。
妊娠中の方、これから出産をお考えのあなたにおすすめ!
妊娠中でも入れる医療保険について詳しく見る
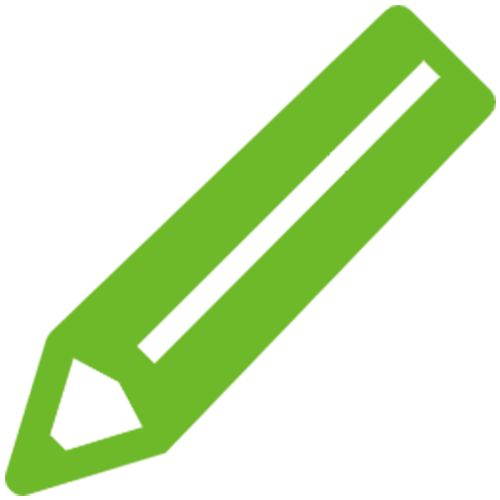 この記事の執筆者
この記事の執筆者

執筆者関野みき
SEOを意識した健康・美容・フィットネス・エンタメ・スポーツなどの記事を数多く執筆した経験あり。保険会社の帳票作成システムの開発経験があり、出産経験があり現在も育児中。
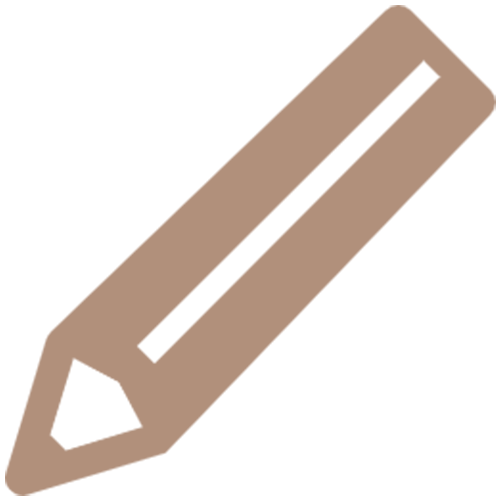 この記事の監修者
この記事の監修者

監修者ファイナンシャルプランナー 三浦希枝
FP3級を保持。保険会社に勤めていた経験を持ち、現在は、フリーライターとして独立起業し、3人の子供を育児中。大手メディアでの執筆経験やセミナー開催で講師の実績もあり。

【吸引分娩は医療保険適用?】適用される場合の必要書類や手続き方法
この記事を見ているあなたは、吸引分娩時に医療保険適用になるのか気になっているのではありませんか。また、医療保険が適用となった場合の費用なども気になりますよね。この記事を見る事で吸引分娩時に保険が適用されることが分かり、安心して出産に臨めるでしょう。
稽留流産や不全流産の手術費用は保険適用!
流産の中でも、胎児(胎芽)が亡くなったあと出血などの症状が出ないまま子宮内に留まる「稽留流産(けいりゅうりゅうざん)」や、子宮内容物の一部が排出されないまま子宮内に残ってしまう「不全流産」は手術が必要になることがあります。
流産手術(子宮内容除去術)の費用は健康保険適用され、自己負担額は3割です。民間の医療保険についても、多くの商品で給付金の支払い対象となります。

流産手術で民間保険の給付金がおりないケースとは
流産手術は基本的に保険適用ですが、自己都合による人工流産(人工妊娠中絶)は健康保険が適用されず全額自己負担となります。民間の医療保険についても給付金はおりず、医療費控除も対象外です。
ただし、妊娠の継続が母体の生命を脅かすと医師が判断したことによりおこなわれる人工流産(人工妊娠中絶)は健康保険が適用されます。民間保険の給付金がおりる可能性もあり、医療費控除についても対象です。
稽留流産の日帰り手術(入院・外来)で民間保険はいくらおりる?
流産手術により民間保険から支払われる給付金の金額は、保険商品や契約内容により異なります。内訳としては手術給付金、入院給付金、女性疾病特約の入院・手術給付金、通院給付金などが支払われる可能性があります。
ただ、同じ契約内容の人が同じ手術を受けても、給付金額が変わることがあります。それは、日帰り手術の場合です。日帰り手術は入院扱いの場合と外来扱いの場合があり、民間保険の契約内容によっては受け取れる給付金が大きく変わります。
例として、以下の場合に支払われる給付金が入院・外来でどのくらい違うのか比較してみましょう。稽留流産の日帰り手術で手術後2回の通院要した場合を前提条件とします。(入院1日目から保障)
| 入院給付金 | 日額1万円 |
|---|---|
| 入院手術給付金 | 一時金10万円 |
| 通院手術給付金 | 一時金2万5,000円 |
| 女性疾病入院給付金 | 日額5,000円 |
| 退院後通院給付金 | 日額5,000円 |
※実際の給付金額は、保険商品や契約内容により異なります。
「入院」して稽留流産の日帰り手術をした場合
今回の契約内容の場合、入院して日帰り手術をおこなった際に支払われる給付金は以下の通りです。
| 入院給付金 | 日額1万円×1日 |
|---|---|
| 入院手術給付金 | 一時金10万円 |
| 通院手術給付金 | - |
| 女性疾病入院給付金 | 日額5,000円×1日 |
| 退院後通院給付金 | 日額5,000円×2日 |
| 合計 | 12万5,000円 |
今回は入院給付金が日額の契約ですが、一時金(入院1回につき〇万円)が支払われる契約であれば、もっと額が大きくなるでしょう。
ただし、一時金での契約は長期入院になると心もとなく、一長一短です。好みに合わせて選ぶと良いでしょう。日額と一時金の両方が受け取れる商品も存在します。

保険商品によっては「10日以上の入院から保障」のような条件がついていることもあるため、保険選びの際は金額以外の条件もしっかり確認することが大切です。
「外来」で稽留流産の日帰り手術をした場合
今回の契約内容の場合、稽留流産の手術を外来でおこなった際に支払われる給付金は以下の通りです。
| 入院給付金 | - |
|---|---|
| 入院手術給付金 | - |
| 通院手術給付金 | 一時金2万5,000円 |
| 女性疾病入院給付金 | - |
| 退院後通院給付金 | - |
| 合計 | 2万5,000円 |
今回の例では入院と外来で手術給付金の金額が異なる契約であり、外来では入院給付金も当然支払われないため、入院した場合と比較してかなり差が出る結果となりました。
入院すれば日帰りであっても入院費がかかるため、民間保険に加入しているからといって必ずしも入院の方が得とは限りません。しかし、通院給付も入院を前提として支払われることが多く、契約内容によっては入院より外来の方が大幅に給付金額が少なくなることも事実です。
稽留流産や不全流産の手術にかかる費用はいくら?
稽留流産や不全流産により手術が必要になった場合、大体どのくらいの費用がかかるのでしょうか。まず、流産手術・子宮内容除去術の診療報酬点数(金額)を見てみましょう。
| 手術 | 診療報酬点数※ | 3割負担の金額 |
|---|---|---|
| 子宮内容除去術(不全流産) | 1,980点 | 5,940円 |
| 流産手術・妊娠11週まで(手動真空吸引法) | 4,000点 | 1万2,000円 |
| 流産手術・妊娠11週まで(その他のもの) | 2,000点 | 6,000円 |
| 流産手術・妊娠11週を超え妊娠21週まで | 5,110点 | 1万5,330円 |
※1点=10円
※2022年現在の診療報酬点数
表を見ていただければ分かる通り、流産手術の費用は3割負担で6,000円〜1万5,000円ほどです。その手術費に加え、診察、検査、麻酔、薬剤などの費用がかかります。入院するのであれば入院費も必要です。
それらの金額を合計すると大体いくらぐらいになるのか、流産手術にかかる費用の相場を早期流産と後期流産にわけてご紹介します。治療内容や入院日数、医療機関によっても金額は異なりますが、大まかな目安として参考にしてください。
早期流産の手術にかかる費用
早期流産の手術は、日帰り手術か1泊2日の入院でおこなわれることが多くなっています。
例えば、日帰り入院で流産手術(その他のもの)を受けた場合、手術費用に加えて検査や麻酔などの費用がかかり、3割負担でトータル1万5,000円程度になります。外来扱いであれば1万円程度で済むこともあるでしょう。

入院日数が延びる、個室に入る、診療報酬点数の高い手術をおこなうなどにより自己負担額が増えることもありますが、その場合でも5万円程度に納まることが一般的です。
後期流産の手術にかかる費用
後期流産では、胎児や胎盤が大きいため手術で取り出すのが困難であることも多く、その場合は陣痛を起こして分娩することになります。そのため、入院日数や費用は通常の出産と同じくらいかかります。
相場としては健康保険適用分が約5万円、分娩介助料などの自費分が約40万円で、トータルすると45万円ほどです。ただし、自費の部分は医療機関が自由に金額を設定できるため、地域や病院によってかなり差があることを覚えておきましょう。

死産は法的に妊娠12週以降の分娩のことを意味し、流産は医学的に妊娠22週以降が定義とされています。妊娠12週以降の流産は法律上死産となるため、赤ちゃんは遺体という扱いになります。この場合、埋葬が必須となります。
流産手術に民間保険以外の保障はある?いくら貰える?
初期流産の手術費用はそこまで大きな額になりませんが、後期流産(妊娠12週以降の流産)は金額が大きいことに加え、産後休業を必ず取らなければならず収入も減少します。その代わり、経済的負担を軽減するための公的保障が用意されています。
ここでは、後期流産の際に利用できる2つの公的保障をご紹介します。なお、今回ご紹介するのは概要のみですので、詳しい事が知りたい方はご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。
出産育児一時金
後期流産をした場合は、妊娠して4ヵ月(85日)以上経過しているのでれば出産として扱われ、健康保険から出産育児一時金が支払われます。
支払われる金額は、産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産(妊娠22週目以降の死 産を含む)した場合は、1児につき420,000円です。この制度に加入していない分娩機関で出産した場合、もしくは妊娠12週以上22週未満の死産・流産の場合は390,000円が支給されます。

ほとんどの医療機関で直接支払制度(出産育児一時金が医療機関に直接支払われる制度)を利用できるため、基本的に窓口負担は出産育児一時金を差し引いた金額になります。
出産手当金
働いている女性が後期流産した場合、流産した日の翌日から8週間の産後休業を取得でき、そのうち6週間は本人が就労を希望しても必ず休業しなければならない期間です。産後休業を取得している期間に会社から給与を十分に受け取れない場合、健康保険から出産手当金として1日につき標準報酬日額の2/3が支払われます。

会社の健康保険に加入していれば契約社員やアルバイトでも出産手当金を受け取れます。しかし、自営業やフリーランスなど国民健康保険に加入している方は、残念ながら対象るため、民間の生命保険などでしっかりリスクに備えておく必要があると言えるでしょう。
まとめ:流産手術は保険適用!民間保険で費用が黒字になることも
流産手術は健康保険適用です。後期流産では費用が高額になりますが、公的保障も利用できるものを活用することで負担を軽減できます。民間の医療保険についても、給付金が支払われる可能性があるため加入内容や給付金が受け取れる条件を確認しておくと安心です。
ただし、早期流産では日帰りや1泊2日など短期入院になることが多いので、加入中または加入予定の保険が短期入院や日帰り手術に対応しているか必ず確認しておきましょう。
日本産科婦人科学会によると、医療機関で確認された妊娠のうち15%が残念ながら流産になります。また、妊娠経験がある女性のうち40%が流産を経験しているというデータもあります。
どんな備えをしていても赤ちゃんを亡くしたことに対するショックを和らげることはできませんが、多くの女性が経験することだからこそ、せめて金銭的な負担だけでも取り除けるよう備えておくと良いでしょう。

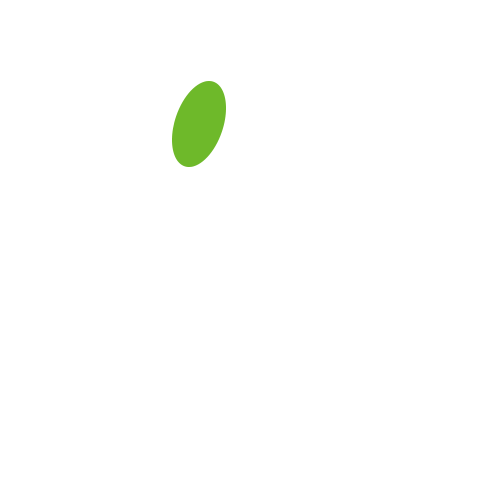 こちらの記事もおすすめ!
こちらの記事もおすすめ!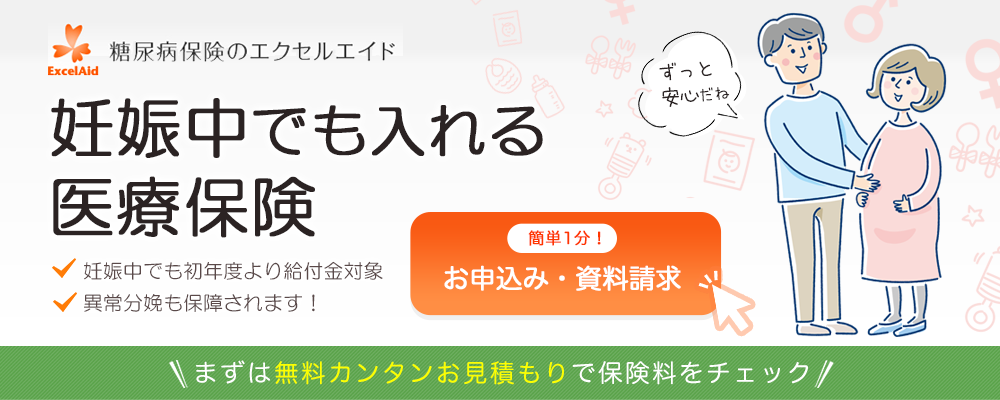
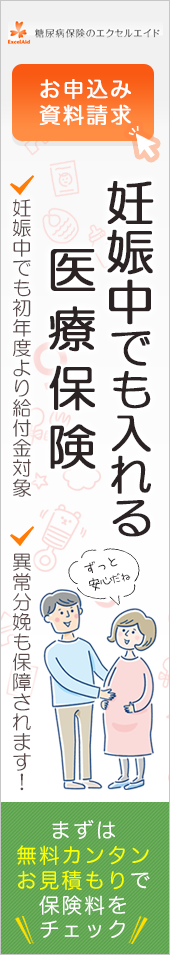
ただし、手術の診療報酬点数(金額)が一定以上でなければ給付金がおりないなど、支払い対象となる手術が限られている民間の保険商品もあります。