正常分娩時の会陰切開、陣痛促進剤使用、吸引分娩は保険適用される?

妊娠が発覚すると正常分娩が保険適用になるのか。加えて、会陰切開、陣痛促進剤使用、吸引分娩などの処置をした際に保険適用となるのか気になりませんか。
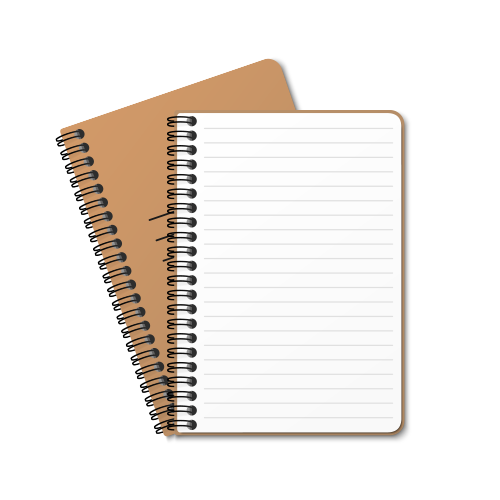
この記事の内容をまとめると
- 正常分娩は基本的に保険適用とはならないが、手術をする場合には保険適用となる
- 会陰切開、陣痛促進剤の使用は正常分娩の範囲内として判断される事が多く保険適用とならない事が多い
- 吸引分娩は異常分娩と判断される事が多く、保険適用になる可能性が高い
- 正常分娩では、出産一時金、出産手当金、育児休業給付、医療費控除などの公的補助を使用するのがおすすめ
この記事を見る事で出産に備えて保険に加入したり見直しをし、安心して出産に臨めるでしょう。
妊娠中の方、これから出産をお考えのあなたにおすすめ!
妊娠中でも入れる医療保険について詳しく見る
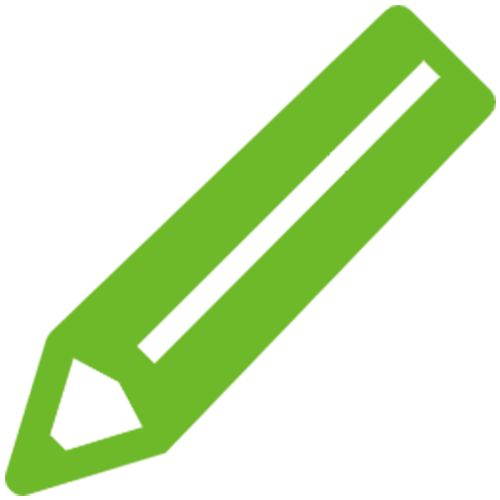 この記事の執筆者
この記事の執筆者

執筆者三浦希枝
FP3級を保持。保険会社に勤めていた経験を持ち、現在は、フリーライターとして独立起業し、3人の子供を育児中。大手メディアでの執筆経験やセミナー開催で講師の実績もあり。
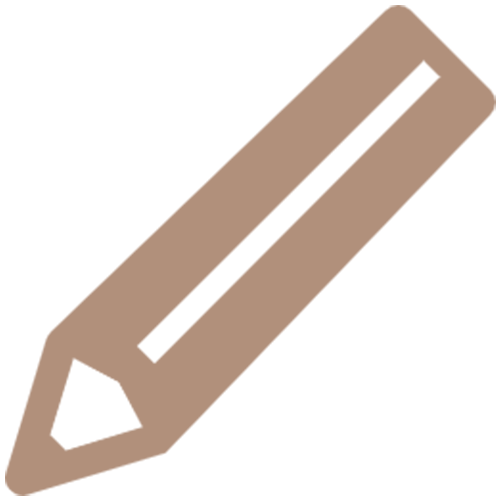 この記事の監修者
この記事の監修者
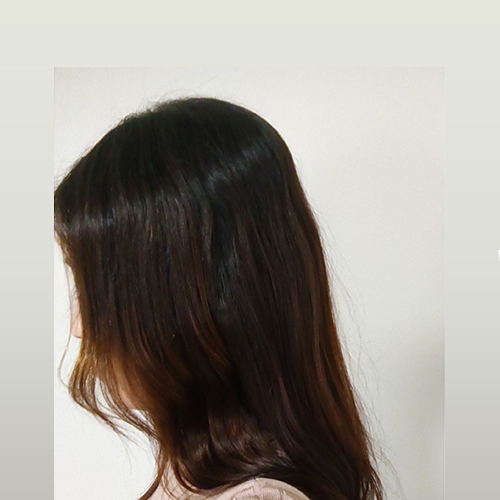
監修者さくらやま
FP2級を保持。現在までに200記事以上を執筆し、正確なリサーチ力を元にさまざまな分野についての知識を深める。現在は、12歳と5歳の息子を育児中。
正常分娩とは
正常分娩とは、正常分娩は37週から41週の間に自然に陣痛が始まって、産道を通って赤ちゃんが出産されることを意味します。
また、分娩にかかる時間は初産婦で12〜30時間、経産婦で5〜15時間以内が正常分娩の範囲となっています。

正常分娩は保険適用になる?
正常分娩は基本的に保険の適用外となります。妊娠・出産は病気ではないため、健康保険など公的な保険と民間の保険どちらに対しても適用外となるのが一般的です。
しかし、妊娠に関わる症状で病気だと医師が判断し、治療や処置の必要が認められた場合のみ、保険が適用されます。公的な健康保険が適用されると自己負担は3割に抑えられるため、金銭的な負担が軽減されます。

健康保険適用となると、高額療養費制度の対象にもなり、民間の保険に加入していた場合はその給付金が受け取れる場合もあるため、より金銭的な負担が軽減されます。
会陰切開、陣痛促進剤の使用、吸引分娩は保険適用される?
ここでは、分娩時に会陰切開や促進剤を用いた場合、吸引分娩となった場合の保険適用の有無について詳しく解説していきます。
会陰切開
正常分娩時の会陰切開は手術としてみなされないため、保険適用にはなりません。
ただ、赤ちゃんが産道からなんらかの理由で出てこられず、鉗子分娩や吸引分娩に切り替えなければならなくなった際の会陰切開は保険適用されます。なお、会陰切開を行うケースとしては、下記になります。
- 赤ちゃんが巨大児で会陰の傷が大きくなる可能性がある
- 赤ちゃんの様子を測る胎児モニターで早急な出産が求められた
- 会陰が進展せず裂傷になる可能性がある
自分の出産は会陰切開のリスクが高いかどうかを確認しながら、万が一の場合に備えて民間の保険の加入状況を確認しておくと安心です。
陣痛促進剤の使用
会陰切開と同じく、陣痛促進剤についても正常分娩時の使用は保険適用外となります。
しかし、ハイリスク妊娠となる方や微弱陣痛が長時間続いているなどの場合については、医療行為とみなされ保険適用となるケースがあります。
- 前期破水をした
- 母親が肥満である
自分がハイリスク出産に該当するのかは、妊婦検診時に医師から伝えられているケースが多く、別途カウンセリングや指導を受けている方もいます。

妊婦が肥満な場合は、食事(栄養)指導もあり、これも医療行為とみなされ保険が適用されます。
吸引分娩
吸引分娩の多くは異常分娩の際に行われるため、保険適用となります。しかし、正常分娩の範囲内で行われた場合は保険適用されないので注意が必要です。
吸引分娩が行われる可能性としてはこちらが当てはまります。
- 胎児の心音が低下した場合
- 母親が妊婦高血圧症や心疾患を発症している
- 分娩の進行が止まってしまった
医師が必要だと判断した場合は医療行為として吸引分娩を取り入れて分娩措置が行われます。また、吸引分娩でも安全ですみやかに分娩が進まなかった場合は帝王切開術に移行する事になります。帝王切開術になって出産した場合は帝王切開術についても保険適用になります。
正常分娩では公的補助を活用するのがおすすめ
正常分娩での出産には基本的に公的な保険(健康保険)をはじめ、民間の保険も適用除外となってしまいます。多額の費用がかかるため、下記のような補助を最大限に活用し少しでも経済的な負担を軽減しましょう。
- 出産一時金
- 出産手当金
- 育児休業給付
- 医療費控除
手続き方法や受け取れる金額、受け取れる条件について確認しておきましょう。
出産一時金
| 条件 | 妊娠4か月(85日)以上で出産をした場合 |
|---|---|
| 金額 | 1児につき42万円(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は40.8万円) |
| 手続き方法 |
※直接支払制度、受取代理制度、直接申請の3つの申請方法のうち、直接支払制度を利用する場合 |
出産一時金は、1児につき42万円(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は40.8万円)を受け取る事ができる補助金です。多胎児出産となった場合は、胎児の人数分の給付金が受け取れるため、分娩費用をはじめ様々な費用に充てられる心強い制度だといえるでしょう。

直接支払制度が利用できる施設であれば、健康保険が医療機関に給付を行い、分娩費用と相殺して賄いきれなかった金額のみ請求されます。
出産手当金
| 条件 |
|
|---|---|
| 金額 | 出産手当金支給以前の12か月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3 |
| 手続き方法 |
|
出産手当金は、働く母親のための制度で、勤め先の健康保険に加入していることが条件に挙げられる制度です。

入金までは2か月程度かかるため、多少のタイムラグはあるものの、受け取る際はまとまった金額のため、金銭的な負担が軽減されるでしょう。
育児休業給付
| 条件 | 育児休業を開始する日の前2年間に雇用保険の被保険者期間が12か月以上あること |
|---|---|
| 金額 | 休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%) |
| 手続き方法 |
|
12か月の間に転職していても、健康保険に自分自身が加入していた場合は適用されます。

必要書類や記入事項が多く2か月に1回(もしくは毎月)行う手続きですが、原則どおり会社が行ってくれるケースが多く、その場合は初回のみ書類の用意や記入をするだけで手続き可能です。
医療費控除
| 条件 |
|
|---|---|
| 金額 | 所得金額200万円以下:(1年間に支払った医療費の合計額-民間の保険金などで補填される金額)-(所得金額合計×5%)、所得金額200万円超え:(1年間に支払った医療費の合計額-民間の保険金などで補填される金額)-10万円 ※どちらの場合も最高で200万円 |
| 手続き方法 |
|
医療費控除の額は、所得金額が200万円以下であれば「(1年間に支払った医療費の合計額-民間の保険金などで補填される金額)-(所得金額合計×5%)」、200万円を超える場合は「(1年間に支払った医療費の合計額-民間の保険金などで補填される金額)-10万円」で計算されます。(最高200万円)
まとめ:正常分娩時の会陰切開、陣痛促進剤使用、吸引分娩は保険適用される?
正常分娩の場合、保険は適用されないのが一般的であるとわかっていただけたでしょうか。ただし、妊娠経過や分娩途中でなんらかのリスクがある場合は医師が医療行為として様々な処置を行います。
会陰切開や陣痛促進剤の使用、吸引分娩について、リスクへ対応するための医療行為として行われたなら、各種保険が適用される可能性が高いのです。保険適用にならない場合は、今回解説した様々な公的補助を利用して、金銭的な負担の軽減をするのがおすすめです。
この記事を見たあなたは出産に備えて保険に加入したり見直しをし、安心して出産に臨めるでしょう。

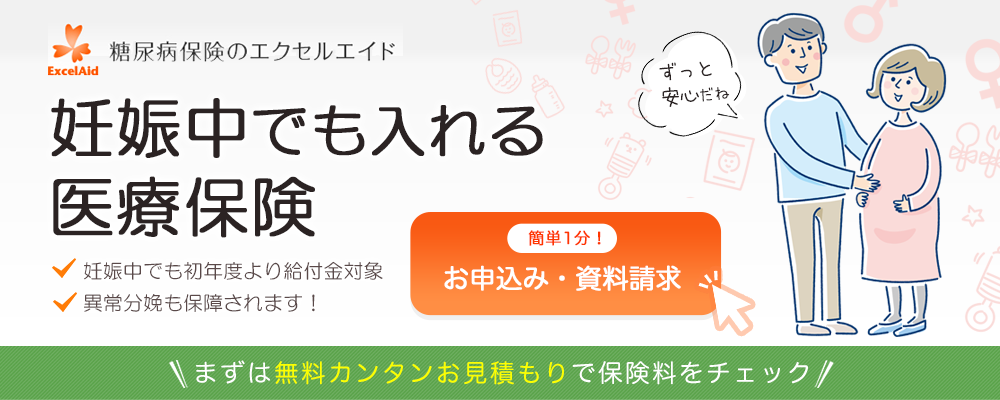
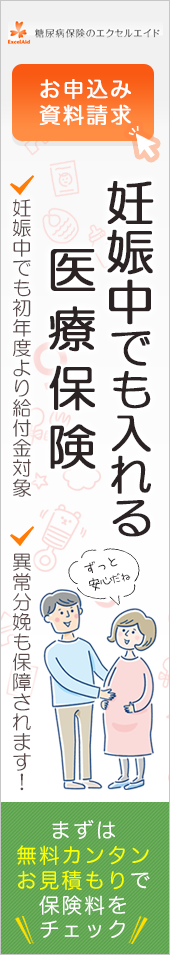
赤ちゃんと胎盤などの付属物が問題なく娩出され、母児ともに障害や合併症などが無く健康であることも正常分娩といわれています。