妊婦必見!限度額適用認定証のイロハ|どこに申請?被扶養者も対象?

この記事を見ているあなたは、限度額適用認定証の申請方法や利用方法を、詳しく知りたいとお考えではありませんか。
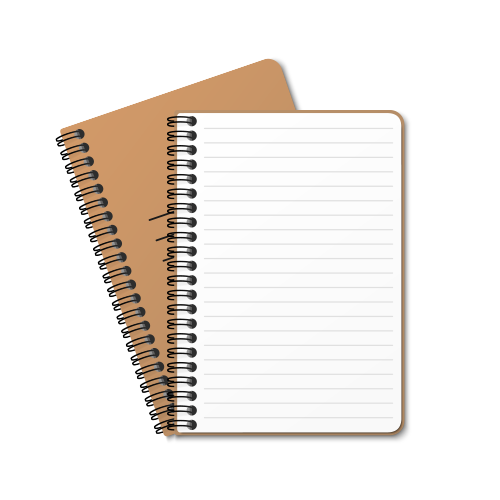
この記事の内容をまとめると
- あらかじめ限度額適用認定証の交付を受けておけば、医療機関・薬局の窓口負担が自己負担限度額までになる
- 世帯合算で自己負担限度額を超えれば、高額療養費の給付対象になる
- 限度額適用認定証の申請先は保険者(会社経由または自分で申請)
- マイナンバーカードを利用できる医療機関・薬局は、限度額適用認定証の申請不要
- 限度額適用認定証が間に合わなかったときは、あとで高額療養費の払い戻しを受ける必要がある
- 妊婦が限度額適用認定証を利用するケースとしては、重症妊娠悪阻や切迫早産による長期入院、帝王切開などが挙げられる
この記事を読めば、限度額適用認定証についての理解が深まり、いざというときも高額な窓口負担を防ぐことができるでしょう。
妊娠中の方、これから出産をお考えのあなたにおすすめ!
妊娠中でも入れる医療保険について詳しく見る
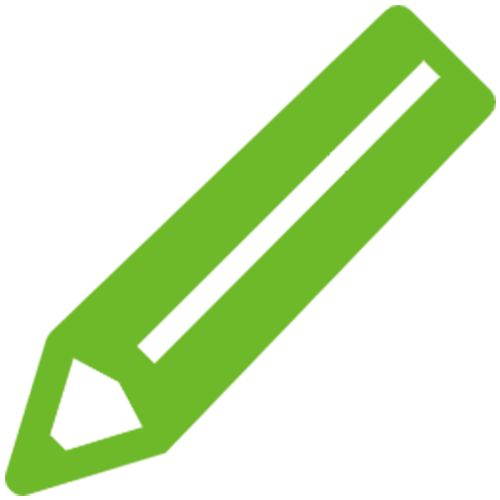 この記事の執筆者
この記事の執筆者

執筆者関野みき
SEOを意識した健康・美容・フィットネス・エンタメ・スポーツなどの記事を数多く執筆した経験あり。保険会社の帳票作成システムの開発経験があり、出産経験があり現在も育児中。
被扶養者も対象!妊婦さんにおすすめの「限度額適用認定証」事前申請とは
医療費負担が重くなりすぎないよう、ひと月当たりの自己負担限度額を定めている制度を「高額療養費制度」といいます。その高額療養費制度を、より便利に利用するためにあるのが「限度額適用認定証」です。
出産を控えている人は、予想外の入院・手術で医療費が高額になったときのために限度額適用認定証の交付を受けておくと、いざというときに助かります。
高額療養費制度や限度額適用認定証に関する知識は、妊娠・出産に限らず病気やケガをしたときにも役立つので、この機会にしっかり理解を深めましょう。
高額療養費制度の仕組み
「高額療養費制度」は、ひと月(1日~月末日)の医療費が自己負担限度額を超えたとき、その超えた分が健康保険(公的医療保険)から払い戻される制度です。健康保険(公的医療保険)が適用される医療費のみ対象となります。
自己負担限度額は、被保険者の所得により金額が変わるので、下表を参考にしてください。
69歳以下の自己負担限度額
| 適用区分 | 自己負担限度額(世帯ごと) | |
|---|---|---|
| ア | 年収約1,160万円~ 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
| イ | 年収約770~1,160万円 健保:標準報酬月額53万~79万円以上 国保:旧ただし書き所得600万超~901万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
| ウ | 年収約370~770万円 健保:標準報酬月額28万~50万円以上 国保:旧ただし書き所得210万超~600万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
| エ | ~年収約370万円 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 | 57,600円 |
| オ | 住民税非課税者 | 35,400円 |
※自己負担限度額の計算に用いる「医療費」とは、1ヶ月間の総医療費(10割)です
※70歳以上の自己負担限度額は厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」を確認してください
高額療養費制度は、ひと月あたりの上限額を設ける制度なので、月をまたいで高額な医療費がかかった場合は、それぞれの月ごとに上限額までの支払いが必要です。入院についても「支払い日」ではなく「受診日」が基準なので、入院期間が月をまたぐかどうかで自己負担額が大きく変わることになります。

合算するときのポイント
- ひとつの医療機関あたり自己負担額が2万1,000円以上の場合のみ合算可
- 70~74歳の人の医療費は2万1,000円未満でも合算可
- 75歳以上の人は制度体系が異なるので合算不可(75歳以上同士は合算可)
- 受診者別、医療機関別で、入院・外来・医科・歯科は分けて計算する
- 調剤薬局で調剤を受けた場合は、処方箋を交付した医療機関に自己負担額を含める
例:適用区分ウの夫婦(同じ健康保険の被保険者と被扶養者)
| ひと月の自己負担額 | 合算可否 | 世帯合算 | |
|---|---|---|---|
| 夫 | A病院(医科・入院)8万円 | 可 | 世帯合算後の自己負担額8万円+3万円+(2+1)万円=14万円 自己負担限度額8万100円+(466,667-267,000)×1%=8万2,097円 高額療養費制度からの給付額5万7,903円 |
| A病院(医科・通院)2万円 | 不可 | ||
| A病院(歯科・通院)3万円 | 可 | ||
| 妻 | A病院(医科・通院)2万円B薬局(A病院の処方)1万円 | 可 | |
| C病院(医科・通院)2万円 | 不可 |
自己負担限度額に達した月が過去12ヶ月以内に3回以上ある場合は、4回目から多数回該当となり自己負担限度額が下がります。詳細は、厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をご確認ください。
「限度額適用認定証」とは
高額療養費制度には、次のような問題点があります。
- 該当の都度、申請が必要
- 払い戻しまでの間、高額な医療費を立て替えておかなければならない
- 払い戻しまで時間がかかる(早くても診療月から3~4ヶ月後)
これらの問題点を解消できるのが「限度額適用認定証」です。限度額適用認定証を医療機関・薬局の窓口に提示すれば、窓口負担が自己負担限度額までとなります。有効期限内であれば、回数に制限なく利用可能です。
ただし、複数の医療機関を受診した場合は、それぞれの医療機関で自己負担限度額までの支払いが発生します。また、同じ医療機関であっても、入院と通院はそれぞれ自己負担限度額までの支払いが必要です。

複数の医療機関への支払い等により上限額を超えた場合は、高額療養費の申請をして払い戻しを受けてください。なお、前月にさかのぼって適用することはできないので、限度額適用認定証が間に合わなかった月は、あとから高額療養費を受け取ることになります。
妊娠・出産で「限度額適用認定証」を利用できるケース|吸引や促進剤は?
妊娠・出産で限度額適用認定証を利用するケースとしては、次のようなものが挙げられます。
妊娠中
- 重症妊娠悪阻
- 妊娠高血圧症候群
- 子宮頸管無力症
- さかご
- 前置胎盤
- 前期破水
- 切迫流産・切迫早産
- 流産・早産
出産時
- 帝王切開
- 吸引・鉗子分娩
- 微弱陣痛などによる陣痛促進剤
- 会陰裂傷(軽傷のものは対象外)
- 無痛分娩の麻酔(医師が医学的に必要と判断した場合)
- 死産
その他、健康保険(公的医療保険)が適用されるものであれば対象です。重症妊娠悪阻や切迫早産で入院が長引く場合や、帝王切開など手術費用が高額なものについては、自己負担限度額を超える可能性が高くなります。
吸引分娩や陣痛促進剤については費用がそこまで大きな金額にはならないので、それ単体で自己負担限度額を超えることは基本的にありませんが、入院期間が長引けば超える可能性はあります。
ただ、出産費用については、帝王切開などの異常分娩となっても全額が健康保険適用となるわけではなく、分娩介助料や赤ちゃんの産後ケア費用などは自費です。そのため、窓口では自己負担限度額+自費分の支払いが必要になります。
それでも、出産育児一時金の直接支払制度と併用すれば、窓口負担はかなり抑えられます。

帝王切開などの予定が特になくても、出産を控えている人が念のため限度額適用認定証の交付を受けるのは(結果的に使わなくても)問題ないので、万が一の場合に窓口負担を抑えたい人は事前申請しておくと良いでしょう。
限度額適用認定証はどこに申請する?会社経由は可能?申請書の書き方も解説
お勤めの方は基本的に会社を経由して申請をおこなうことになります。限度額適用認定証が必要になりそうなときは、早めに勤務先の担当者に確認しましょう。国民健康保険の加入者など、ご自身で手続きをする場合は、以下の内容を参考にしてください。
限度額適用認定証の申請先
- 国民健康保険:お住まいの市区町村の役所(国民健康保険係の窓口)
- 上記以外(協会けんぽなど):保険証に記載されている保険の所属支部
限度額適用認定申請書の書き方は?協会けんぽを例に解説
限度額適用認定証の申請書様式は保険者により異なりますが、ここでは協会けんぽを例に書き方をご紹介します。協会けんぽの申請書や添付書類用の貼付台紙は、こちらからダウンロードしてください。協会けんぽ「健康保険限度額適用認定申請書」
申請書に記入する内容は、次の通りです。
- 被保険者情報:被保険者の記号・番号、生年月日、氏名、住所、電話番号
- 認定対象者欄:療養を受ける人の氏名、生年月日、療養予定期間
- 送付希望先:被保険者情報と違う住所に認定証の送付を希望する場合
- マイナンバー:被保険者情報の記号・番号を記入した場合は不要
間違いやすいのは「被保険者情報」の記入欄です。被保険者情報欄には、認定を受ける人の情報ではなく被保険者の情報を書く必要があります。例えば、夫の健康保険の被扶養者である妻が認定を受けるときは、被保険者情報欄に夫の情報、認定対象者欄に妻の情報を記入してください。
マイナンバーを記入した場合は、次のいずれかを貼付台紙に貼って、申請書に添付します。
- マイナンバーカード(表面・裏面)のコピー
- 通知カードなどのコピー+写真付き身元確認書類のコピー

申請書の郵送先は、保険証発行元の支部です。住所は、協会けんぽ「全国健康保険協会支部」から確認できます。協会けんぽ以外の健康保険(公的医療保険)に加入している方は、ご加入の保険組合等のホームページをご確認のうえ、手続きをおこなってください。
マイナンバーカードを利用できる医療機関では事前申請不要
マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関・薬局では、オンラインで資格確認ができるため、限度額適用認定証の事前申請は必要ありません。情報提供の同意をするだけで、窓口負担が自己負担限度額までになります。
このシステムは、令和5年4月から医療機関・薬局に導入が義務化される予定です。
情報提供の同意方法
- マイナンバーカードを利用する場合:顔認証付きカードリーダーで情報提供に同意
- 保険証を利用する場合:口頭で情報提供に同意
同意により医療機関・薬局に提供される情報
- 保険者番号
- 被保険者証記号・番号
- 枝番
- 限度額適用認定証区分
- 自己負担限度額を算出する際の適用区分
- 交付年月日
- 回収年月日
- 長期入院該当年月日(減額認定証の交付対象者)
上記システムを利用できない医療機関・薬局にかかる場合や、食事療養費の減額対象者(住民税非課税かつ過去12ヶ月の入院日数が90日超の人)、国民健康保険料の滞納がある世帯は、引き続き限度額適用認定証の交付申請が必要です。
限度額適用認定証が出産に間に合わない場合の対処法
限度額適用認定証は、申請から数日~1週間程度で交付されることが多いようです。もし出産に限度額適用認定証が間に合わなくても、入院してすぐ会社や家族に手続きを頼めば、退院までに間に合う可能性があります。
月の途中で限度額適用認定証の交付を受けた場合は、当月中に窓口へ提示すれば月初にさかのぼって適用されます。ただし、前月にさかのぼって適用を受けることはできません。
限度額適用認定証が間に合わなかった場合は、一時的に3割負担のすべてを支払い、あとから高額療養費を請求することになります。高額療養費の請求方法は、保険者によりさまざまです。
該当すると申請用紙を送付してくれたり、特に申請しなくても自動的に高額療養費を支給してくれたりする保険者もあれば、自身で申請しない限り支給されない保険者もあります。ホームページなどで手続き方法を確認してください。

高額療養費の申請から給付までは早くても3~4ヶ月かかるので、申請手続きが必要な場合は早めにおこないましょう。給付を受ける権利の消滅時効は、診療月の翌月1日から2年です。
まとめ:妊婦さんは限度額適用認定証の事前申請をしておくと便利!
妊娠中は、通常時に比べはるかに入院・手術のリスクが高くなります。思わぬ長期入院や帝王切開など、予想だにしない高額の出費に備えるためにも、出産前に限度額適用認定証の交付を受けておくと便利です。
マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関・薬局では、限度額適用認定証がなくても、情報提供の同意だけで窓口負担を自己負担限度額までに抑えられます。交付申請の前に、限度額適用認定証が必要な医療機関・薬局なのか確認しておくと良いでしょう。
前月にさかのぼって認定を受けることはできないので、限度額適用認定証が間に合わなかったときは一旦自身で支払い、あとから高額療養費を受け取る必要があります。
医療機関からの診療報酬請求に基づき、自動的に高額療養費を支給してくれる保険者もありますが、ご加入の健康保険(公的医療保険)によっては自分から申請しない限り高額療養費の給付は受けられません。ホームページ等で、手続き方法を確認しておくことをおすすめします。
高額療養費制度・限度額適用認定証を利用して、妊娠・出産時の医療費負担を上手に抑えましょう。

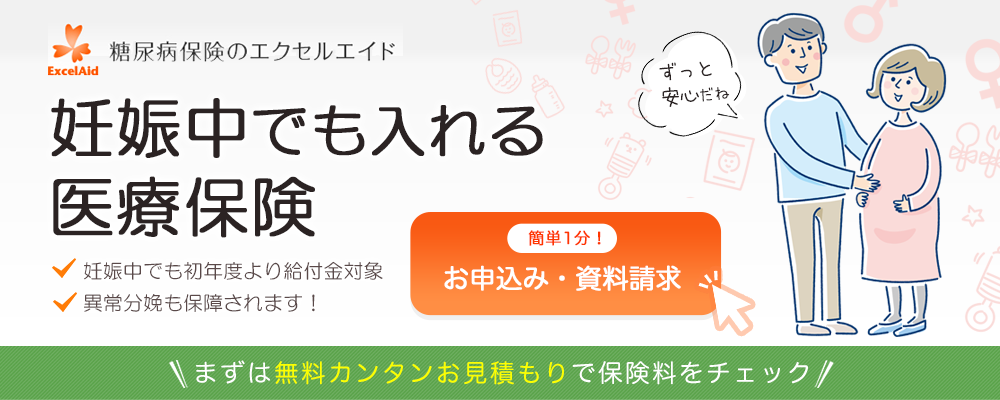
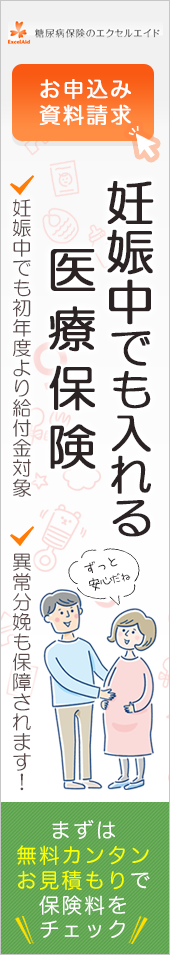
ひとつの医療機関で自己負担限度額を超えなくても、違う医療機関の受診や、同じ世帯の人(同一の健康保険に加入している人)の受診を合算して超えれば、高額療養費の給付を受けられます。